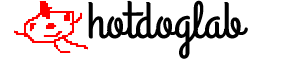桃の節句だけじゃない!五節句の由来
節句と言えば何?
たぶん、多くの人が思うのは、桃の節句と端午の節句ではないかと思います。
今日では、ほとんどこの2つしかないようなものです。
でも、本当は五節句と言って、5つあるんですよ。
昔から節句の日にはみんな休んで行事を行っていたそうです。
暦の上でも重要な位置づけだったみたいです。
今回は五節句とその由来についてです。
五節句とは?
五節句にはどんな日があるのでしょうか。
1月7日…人日(じんじつ)
3月3日…上巳(じょうし)
5月5日…端午(たんご)
7月7日…七夕(しちせき)
9月9日…重陽(ちょうよう)
これが五節句と言われる5つの日です。
せっかくなので、意味とか成り立ちも書きますね。
人日(1月7日)の由来。
1月7日の人日は、人の日という意味なんですね。
じゃあ、ほかの動物の日もあるのかなって思った方、正解です。
1月の1~6日はほかの動物の日です。
昔の中国の話。
1月の1~6日は動物を占って、7日には人を占うという風習があったそうです。
1月1日は、鶏の日。
1月2日は、狗(いぬ)の日。
1月3日は、猪の日。
1月4日は、羊の日。
1月5日は、牛の日。
1月6日は、馬の日。
そして、やっと1月7日、人の日です。
これらの日にはどの動物を殺さないようにするみたいです。
1月7日は人なので、犯罪者の刑罰も行われなかったとか。
悪いことをした人にとってはありがたい幸運な日です。
日本でも江戸時代には人日が幕府の公式な行事として取り入れられて、将軍様をはじめ、七草粥を食べて祝うようになったそうです。
武家にとっては重要な祝日となっていったようですね。
上巳(3月3日)の由来。
上巳の日は、3月3日です。
上巳というのは旧暦の3月上旬の巳の日。
これも中国の昔の話で、この日に川の水で身を清めたことが由来のようです。
日本にも平安時代に取り入れられて、上巳の祓として貴族の間で定着します。
祓のときに使う人形があって、形代というそうですが、それに人の穢(けがれ)を移して、川や海に流し、不浄していたそうです。
これは現代では、流し雛として残ってきました。
流し雛は無病息災などをひな人形に託し、川や海に流すことなんです。
3月3日がひな祭りとして庶民に広まるのは江戸時代。
今では3月3日と言えば、お雛様というイメージが強いですよね。
端午(5月5日)の由来。
端午の節句は、男の子の節句です。
旧暦の5月5日。
端午というのは「初五」という意味。
もともとは月の初めの午の日だったようですが、それが毎月の5日の日となり、とくに5月5日を指すようになったようです。
つまり、昔は5月以外の5日の日も端午だったわけです。
これも中国の風習が由来となっています。
中国では月と日が同じ日を祝日としていました。
だから5月5日を祝います。
この日は薬草を摘んだり、ヨモギで人形を作って玄関に掛けたり、ショウブ湯を飲んだりして、邪気を祓うという行事が行われていたんだとか。
平安時代には日本でも普及。
ショウブやヨモギを軒につるし、ちまきや柏餅でお祝いをします。
それが江戸時代になると、鯉のぼり、甲冑、刀、武者人形などを飾るようになります。
これは子どもの成長を祝う行事として今なお伝統的な行事です。
またショウブ湯に入ることもあるんですね。
これはショウブが薬草で邪気を祓うということが由来なんです。
七夕(7月7日)の由来。
七夕は、旧暦の7月7日。
この日の夜は「たなばた」と言いますよね。
これも中国から伝わってきているものです。
ご存知の通り、彦星と織姫が年に一度、天の川で出会うというものですよね。
1年で一番みんなが星を見る日かもしれません。
日本では奈良時代に取り入れられています。
この頃は、女子の裁縫の上達を祈る行事だったみたいですね。
笹竹を立てて、五色の短冊に詩歌を書き、習い事の上達を願う。
これは江戸時代になってからの風習のようです。
日本独自の文化としては、お盆につながる行事として、水浴びをして穢(けがれ)を祓うという行事も行っていました。
もともと七夕とお盆は1つの流れでもあったんですね。
でも今では、お盆と七夕はそれぞれ違うものとなっていますよね。
青森のねぶた祭りや秋田の竿灯といったお祭りも七夕を由来にしているそうです。
重陽(9月9日)の由来。
重陽は旧暦の9月9日、菊の節句です。
中国では奇数を陽の数としていました。
陽の数の中で1番大きい数字が9で、それが2つも重なるめでたい日。
ということでお祝いをしていたんですね。
日本には平安時代に伝わります。
杯に菊の花を浮かべて酒を酌み交わし、長寿を祝いました。
江戸時代の頃には、この日がかなり重要視されていたみたいです。
武家には菊の花を酒に浸して飲む風習があって、庶民もあわご飯を食べる風習がありました。
五節句は大切に受け継がなきゃ。
五節句は昔からの風習ですね。
形を変えてもちゃんと残っているのは、なんとなく誇らしいことですよね。
私たちもちゃんと未来に受け継いで行かなければいけません。
1月7日は七草粥を食べるし、3月はひな祭りの雰囲気が漂うし、5月5日は鯉のぼりをよく見ます。
7月7日はスーパーとかでも短冊を飾ったりしています。
9月だけ私は意識が薄かったので、今年は1つ1つ気にして過ごしたいなと思います。
関連記事
-

-
【2021年】海外旅行の吉方位と凶方位!今年行くならどこの国?
2021年の海外旅行についてです。 今年は海外旅行は無理でしょうか。 コロナウィ …
-

-
2018年の金神の方位は5方位!遊行と間日など避ける方法も…
金神という神様を知っていますか? 金神は方位の神様の1人です。 方位の神様はたく …
-

-
干支はなんて読む?十干十二支のいろいろ
漢字のテストで普通にありそうな問題。 読み仮名を書く問題です。 “干 …
-

-
旅行は吉方位へ。あなたの旅行先を決めるサイト。
いろいろと作る苦労はありましたが、 「旅行は吉方位へ。旅行先を決めるサイト。」を …
-

-
庚申、甲子、己巳の日とは?
世の中の99%の人は気にしていない日だと思います。 暦にこんな日があるってこと。 …
-

-
鬼門の起源と桃太郎の仲間選抜の疑問
最近は気にする人が少ないと思いますが、方位には「鬼門」っていうのがあります。 こ …
-

-
2018年の大将軍の方位は南!三年塞がりの最後の年、午の方位は避ける!
2018年の大将軍の方位は南です。 もう少し正確に言うと、午(うま)の方位という …
-

-
2015年の凶方位。5大凶殺、八将神、金神はどの方位?
九星気学では360度を8方位に分けて、中央を含めて9つの場所に星が配置されます。 …
-

-
【2023年】九紫火星の旅行や引っ越しの吉方位とタイミング
九紫火星の2023年の吉方位はどこでしょうか。 東です。 ただ、これだけ知ってい …
-

-
【2019年】海外旅行の吉方位!今年行くならどこの国がいい?
2019年の海外旅行、どこに行こうとしていますか? これから決めるのでしたら、ぜ …
- PREV
- 方違えも安心!位置情報を知るGPSの技術
- NEXT
- 語呂合わせの記念日を探してみる